「人生100年時代」と言われても、40代の私たちが直面するのは、期待よりも「不安」です。住宅ローン、子どもの教育費、そして自分たちの老後資金。守るべきものが増える中で、最も避けたいのは、ムダな支出と経済的なリスクです。
私も長年、大手民間保険に加入していましたが、ある日、ふと疑問が湧きました。
「この毎月の保険料、本当に全部が自分の保障のために使われているのか?」
この記事では、私が民間保険から卒業し、いきいきスマイル共済という選択肢にたどり着いた、合理的な思考プロセスを公開します。
1. 民間保険の「広告費」に抱いたモヤモヤ
私が保険を見直すきっかけは、テレビCMでした。
誰もが知る有名俳優を起用した、豪華な映像と大々的な宣伝。企業がブランドイメージを高めるのは理解できますが、**「この莫大な広告費用は、結局どこから出ているんだ?」**と考えると、胃のあたりがモヤモヤしました。
答えはシンプルです。私たち契約者が毎月払っている保険料です。
民間企業である以上、利益を追求し、広告費や営業コスト、株主への配当に資金が流れるのは当然です。しかし、家計を預かる身として、**「自分の将来の安心のための掛け金が、半分近くも広告宣伝費に消えているとしたら…?」**という疑念が、契約を続ける合理性を失わせました。
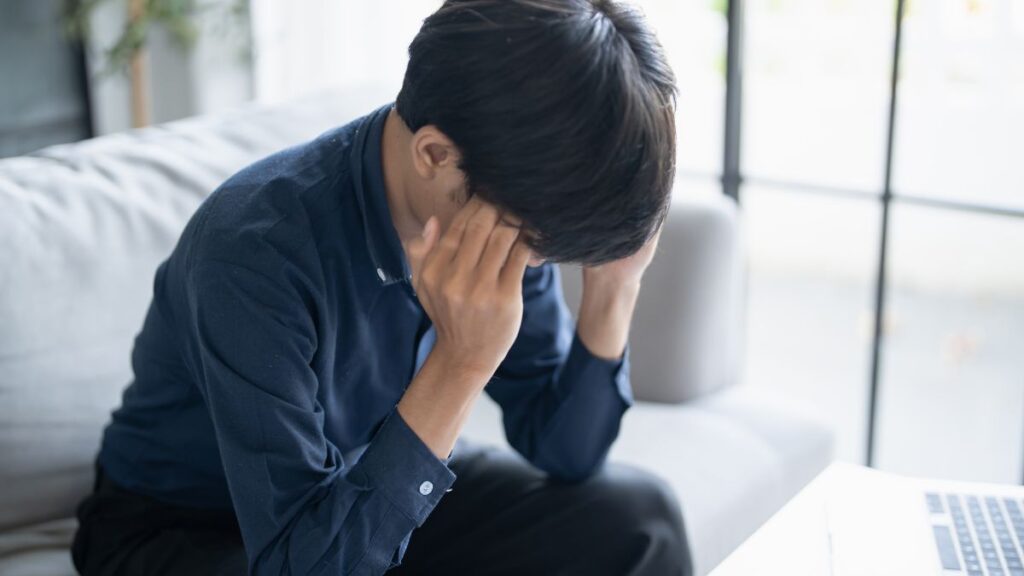
💰 感情論ではなく「費用の合理性」を追求
終身保険などの積み立て型の民間保険は、たしかに老後の安心材料になります。しかし、その高額な保険料が、本当に必要な保障だけでなく、企業の利益構造を支えていると考えると、経済的な合理性に欠けると判断せざるを得ませんでした。
2. 労働組合共済の「非営利」構造が示す合理性
民間保険に疑問を持った私が着目したのが、共済です。
共済は、労働組合や生協といった非営利団体が運営する相互扶助の仕組みです。ここで重要になるのは、「非営利」という言葉が持つ意味です。

🤝 「助け合い」の精神がコストを抑える
- 広告・営業費の抑制: 大々的なテレビCMや豪華なオフィス、高額な営業インセンティブが少ないため、運営コストが極めて低い。
- 掛金が加入者へ還元: 営利を目的としないため、残った剰余金は「割戻金」として加入者に還元される可能性があります。
私の払ったお金が、企業の利益ではなく、「困っている仲間の保障」や「自分自身の還元」に回る。この資金の流れの透明性と合理性が、家計を預かる男として非常に納得できました。
3. 「積立より投資」で老後資金の最適解を追求
保険の見直しを決めたもう一つの大きな理由は、資産形成とのバランスです。
終身保険に多額の資金を「寝かせておく」よりも、その資金をNISAやiDeCoといった堅実な投資に回し、インフレに強い資産として運用する方が、老後資金対策として合理的ではないか?と考えるようになりました。

💡 共済は「掛け捨てOK」と思えるほどの低コスト
- 共済の役割: 共済の役割は、あくまで「万が一の短期的なリスク(医療費など)への備え」に絞る。
- 資金の配分: 月々2,000円〜3,000円程度の低掛金で最低限の安心を確保し、浮いた資金をリスクを取れる投資に回す。
この考え方により、保険は「将来の貯蓄」ではなく「コストの低いリスクヘッジツール」へと役割が変わり、掛け捨てであっても全く気にならなくなりました。
4. 私が「いきいきスマイル共済」を選んだ決め手
いくつかの共済を比較した結果、最終的に私が選んだのは「いきいきスマイル共済」です。
- シンプルさ: 複雑な特約やプランがなく、「入院保障」と「死亡保障」に絞られており、内容が明快で理解しやすい。
- 現実的な保障額: 月額2,800円(例)という手頃な掛金でありながら、病気・事故による死亡や入院への備えとして、必要最低限の保障額が設定されている点。
- 労働組合運営の信頼性: 営利企業ではない、相互扶助を目的とした労働組合が運営しているという背景が、経済的な信頼性を高めました。
「備えすぎず、無保険にもならない」、この「ほどほどの安心」が、40代の我々には最も必要なバランスだと感じています。

結論:広告より「未来の家族」のためにお金を使いたい
私が民間保険から共済に切り替えたのは、感情的な理由ではありません。「自分の払ったお金が、どこに、どれだけ使われているか」という費用対効果と合理性を徹底的に追求した結果です。
私の保険料が、豪華なCMではなく、本当に困った人の医療費に回ること。そして、浮いたお金が、家族のより豊かな未来のための投資に回ること。
安心とは、金額の大きさではなく、そのお金の流れに納得できるかどうかで決まるのだと、共済という選択肢を知って改めて感じました。
もし今、あなたの民間保険のパンフレットを見て「モヤモヤ」を感じているなら、一度「共済」という合理的な選択肢を検討してみることを強くおすすめします。




コメント