スーパーで一度は目にしたことのある「明治おいしい牛乳」。
“おいしい牛乳”という印象的な商品名ですが、実はこの言葉自体は単独では商標登録されていません。
本記事では、「おいしい牛乳」という言葉の正体、「明治おいしい牛乳」が商標として成立する理由、そしてなぜ他社は使えないのかを、法律とマーケティングの両面からわかりやすく解説します。
「おいしい牛乳」は単独では商標登録されていない
意外かもしれませんが、「おいしい牛乳」単体では商標登録はされていません。
日本の商標法では、「単なる品質や特徴を表す言葉」は原則として商標として認められません。
つまり「おいしい」「牛乳」という言葉は一般的すぎて、それ単体では識別力(ブランドとしての区別性)に欠けるとされるのです。

商標登録されているのは「明治おいしい牛乳」
ではなぜ他社は「おいしい牛乳」と名乗れないのでしょうか?
答えは、商標登録の実態にあります。実は、商標として登録されているのは、
- 「明治おいしい牛乳」(登録番号:第4712645号 ほか)
- 「森永のおいしい牛乳」など、社名+おいしい牛乳の形
つまり、「社名」+「おいしい牛乳」という形であれば、ブランドとして識別可能と判断され、登録が認められているのです。
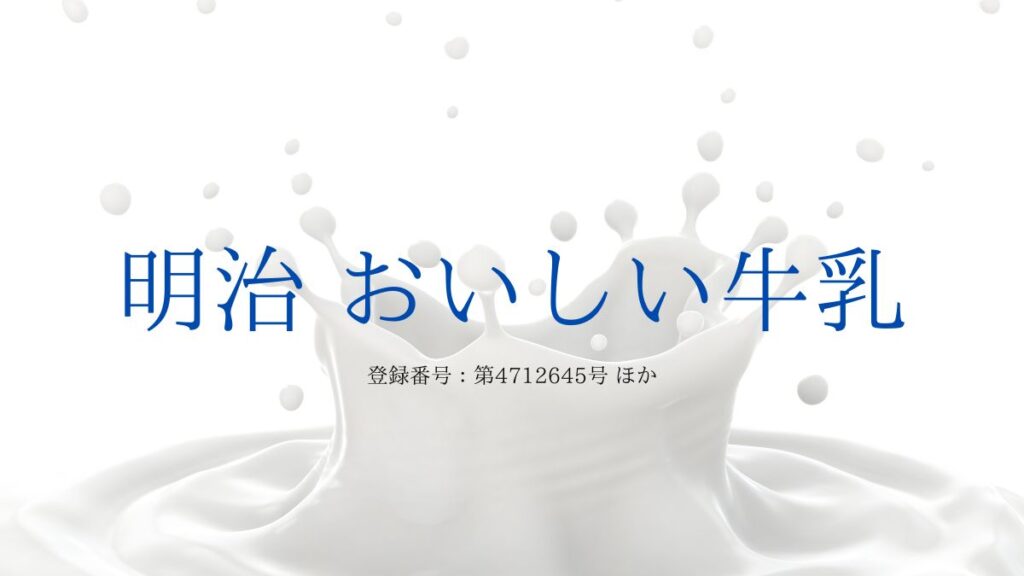
なぜ他社は「おいしい牛乳」を使えない?
仮に他社が「〇〇おいしい牛乳」という名前で商品を出した場合、消費者が「明治の製品かな?」と誤認する可能性があります。
このような場合、商標権侵害や不正競争防止法に抵触するリスクがあり、
実際にネーミングやパッケージが酷似していると、変更を余儀なくされることもあります。
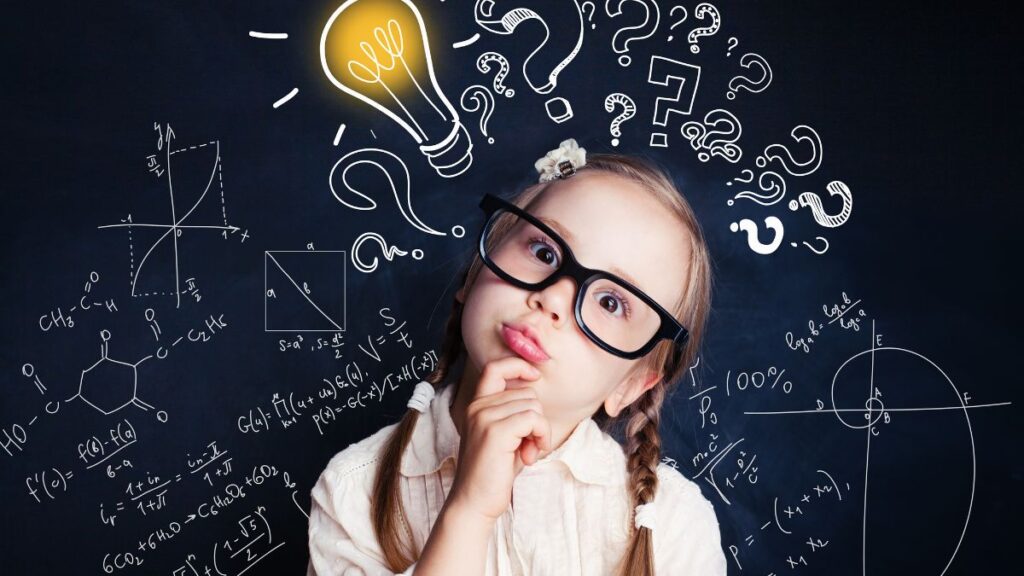
明治のネーミング戦略:「おいしい」を“自社の顔”に
「明治おいしい牛乳」は1999年に発売されて以来、長年愛され続けているブランドです。
特長的なのは、「おいしい」という言葉を堂々と商品名に採用し、品質への自信と親しみやすさを両立した点。
また、独自の「ナチュラルテイスト製法」など技術的な裏付けを徹底することで、
ネーミングと品質が一致したブランド価値を築いてきました。
まとめ:「おいしい牛乳」は誰のもの?
「おいしい牛乳」という言葉そのものは誰でも使える表現ですが、
「明治おいしい牛乳」はれっきとした登録商標です。
したがって、他社が同様の言葉を用いると法的リスクが生じる可能性が高く、事実上は「明治の専用ブランド」として広く認識されています。
このように、何気ないネーミングにも法律と戦略が込められていることを知ると、日常の買い物も少し楽しくなるかもしれませんね。

🔜 次回予告:いつも空いてるのに業績は右肩上がり?
平日はお客さんがまばら、週末でも混雑とは無縁、そんなイメージの西松屋が、実はここ数年で業績を大きく伸ばしているのをご存知ですか?
なぜ“人が少ない”のに利益が出るのか?
その裏には、他社が真似できない独自のビジネスモデルと戦略がありました。
次回は、西松屋の成功のカギを「店舗設計・人件費・物流・顧客戦略」の視点から徹底解説します。




コメント